生物多様性保全機能(森林の持つ公益的機能)
生物多様性保全機能
森林は「生き物の宝庫」といわれるように、世界の陸上動植物の約8~9割にあたる160万種もの生物が暮らしているといわれています。草原や乾燥地帯などに比べても、森林は圧倒的に多様な生き物を育む場所なのです。こうした多様な命を守り続ける働き(遺伝子や生物種、生態系を守り続ける働き)を、「生物多様性の保全機能」と呼びます。

森林には、鳥類、昆虫類をはじめとする多くの野生動植物が生息・生育しています
特に日本は、国土の約7割が森林に覆われ、四季折々の豊かな降水量に恵まれています。そのため、乾燥地帯や高緯度地域と比べても、生物多様性がきわめて高い国のひとつといえます。
森が生き物と人間にもたらす恵み
森林は動物にとって身を隠す場所となり、木々がつくる日陰や湿度の安定した環境は、多くの生き物にとって暮らしやすい条件を与えます。そこに植物や昆虫、鳥や獣が集まり、食物連鎖や複雑な生態系が形づくられていきます。人間もまた、その恵みを受けています。木材や食料の供給はもちろんのこと、森林にはまだ利用されていない薬や工業資源の原料となる可能性を秘めた生物も数多く眠っているのです。
しかし、森林が失われると、こうした生態系のバランスが崩れ、絶滅の危機に瀕する動植物が増え、人間社会にとっても大きな損失となります。未来世代にまで影響が及ぶ可能性も否定できません。
未来へつなぐ森林保全の課題
かつて「日本人は水や空気は無料だと思っている」といわれましたが、森林やそこに息づく生物多様性についても、同じようにその価値が見過ごされがちでした。とはいえ近年では、絶滅危惧種の保護や国や自治体による保全施策、市民の環境意識の高まりによって、少しずつ状況は変わりつつあります。一方で、林業、里山の利用、自然保護など、立場や関心の違いから価値観が交錯し、どのように折り合いをつけて森林を守っていくかが大きな課題となっています。
これからの時代、森林と生物多様性を守るには、行政だけでなく、市民や科学者、地域社会が協力し、広い視野で取り組んでいくことが欠かせません。森林を次世代へつなげるために、私たち一人ひとりも関心を持ち続けることが大切です。
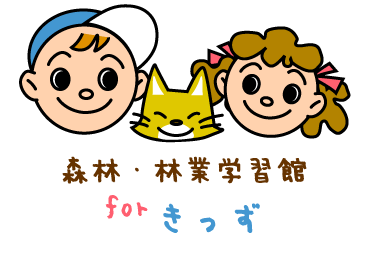
森はどうして「生き物の宝箱」なの?
みなさんは森に入ったことがありますか? 森の中では、鳥の声が聞こえたり、虫が飛んでいたり、いろいろな植物が生えていたりします。実は、森には草原や砂漠よりもずっとたくさんの生き物がくらしているんです。その数は、地球の陸にすむ動物や植物のほとんど、8~9割にものぼるといわれています。
森は生き物のすみか
森は大きな木や小さな草がたくさん生えていて、動物たちにとってすごくすごしやすい場所です。木のかげは夏でもすずしく、落ち葉や草のあいだから小さな虫がかくれることもできます。鳥は枝の上に巣をつくり、リスやサルは木の実を食べます。森はまるで大きなアパートのように、いろいろな生き物がくらしているのです。
森があるから人も助かっている
森に生き物がたくさんいると、「食べる・食べられる」のつながり(食物れんさ)ができあがります。そのおかげで自然のバランスが保たれています。人間も森から木材や食べ物をもらったり、薬のもとになる植物を見つけたりして、大きなめぐみを受けています。
森を守ることは未来を守ること
でも、森がなくなってしまうと、生き物がすめなくなり、絶滅してしまうかもしれません。そうなると自然のバランスがくずれ、私たちの生活にもえいきょうが出てきます。だから、森を大切にすることは、未来の人びとのくらしを守ることにもつながります。

