間伐の種類(定性間伐・定量間伐・列状間伐)
間伐とは
間伐とは、植林木(人工林)の成長過程で過密となった立木の密度を調整するために、一部を抜き伐りする「木の間引き」作業です。苗木を植えてから15~20年ほどすると林内が混み合い、枝葉が重なって光が不足し、根張りも弱くなって健全な成長を阻害します。このため適切な時期に間伐を行います。

木々が密集しており、お互いの成長を阻害している
©2010 私の森.jp 写真部
間伐は林業経営の基礎であり、木々の密度を調整することで、残存木の健全な成長を促進し、風雪害や病虫害に強い健全な森林をつくります。将来、質の高い木材の生産にもつながります。
木々が適度な間隔を保つことで、林床に光が届き、下層植生が繁茂し、土壌浸食や土砂流出の抑制、野生生物の生息環境の改善など、国土の保全や生物多様性の保全など環境面での効果も得られます。
さらに、間伐材の利活用(チップ・合板・集成材・バイオマス利用など)により、地域経済に貢献します。
間伐の実施時期
間伐の実施時期は、樹種や森林の状況によって異なりますが、一般的に晩秋から冬にかけてが適しているとされています。夏に比べて、木が水を吸い上げなくなるため、伐採しやすくなることや、夏に茂っていた草が枯れて作業がしやすくなることが理由です。
間伐の周期
初回間伐後、林分の状況を見ながら5~10年程度の周期で実施されることが多いようです。間伐は林分の状態(樹種・密度・樹高・直径階分布(木の太さのばらつき)・健全度・地形・作業道の状況)を踏まえ、最適な方法と間伐強度(伐る割合)を計画的に決めて実施することが大切とされています。
間伐の課題
間伐は森林を健全に保つために欠かせない作業ですが、実施にはいくつかの課題があります。
まず、伐採や搬出、作業道の整備などに多くの費用がかかる一方で、細い木や質の低い木は市場価値が低く、採算が取りにくいという経済的な問題があります。さらに、林業の担い手不足と高齢化が進み、間伐に必要な経験や技術を持つ人材が限られています。作業現場は急斜面やぬかるみなど危険が多く、路網整備が不十分な地域では搬出も困難です。
また、日本の森林は所有者が細かく分かれており、所有者不明地も多いため、間伐計画の合意形成に時間がかかります。加えて、間伐後に適切な管理が行われないと、風倒被害や病害虫の発生リスクが高まります。さらに、輸入材の増加や住宅需要の変化で国産材の需要が減り、間伐材の利用先が限られていることも課題です。こうした要因が重なり、多くの地域で間伐の実施が難しくなっています。
定性間伐
定性間伐は、木の性質・形質や立木相互の関係を見て伐採木を現場で選ぶ方法です。成長不良木、曲り木(ひょろひょろとした木)、樹幹欠点の大きい木、病虫害木、優良木の成長を圧迫している介在木などを優先して伐ります。一本一本の樹冠発達・幹の通直性・節の状況・根返りリスクなどを見極めるため、仕上がりの質に優れ、主伐期までの価値の高い木材の生産を目指せます。定性間伐は間伐方法として主流となっており、間伐木の選定が大切です。
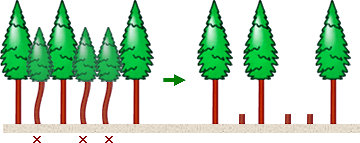
定性間伐のイメージ図
- 長所:優良木を確実に残せる/材質・将来価値の向上/風害等への抵抗性向上。
- 短所:選木に時間と技術が必要/コスト高になりやすい。
定量間伐
定量間伐は、立木の形質や形状よりも、立木の密度に重点を置いて、残す量をあらかじめ決めて行う間伐です。残す本数(または立木密度)や断面積合計(本数比・本数率・本数間伐率・本数残存率、胸高断面積合計など)をあらかじめ決めておき、機械的に伐る割合を配分します。優良木と不良木の比率は間伐前後で変わりませんが、選木にかかる時間を短縮できるというメリットがあります。定量間伐は、経済的な合理性(低コスト)や作業の安全性を考慮した上で採用されることが多いようです。
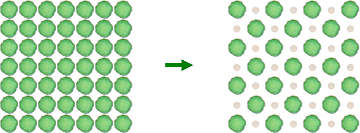
定量間伐のイメージ図
- 長所:選木・施工の効率が高い/コストを抑えやすい/作業計画・安全計画を立てやすい。
- 短所:不良木が残る可能性/優良木を十分に伸ばしにくい。
列状間伐
列状間伐は定量間伐の代表例で、等間隔で列(筋)ごとに伐採する方法です。 斜面上下方向(等高線直交方向)または地形に合わせて列を設定し、例えば「3残1伐」「4残1伐」など、森林の状況により方法を選択します。立木の形質や形状などに関係なく直線的に残るので伐採した列は、間伐木の集材・搬出の作業動線として利用できるようになります。
列状間伐は高性能林業機械(ハーベスタ・プロセッサ・フォワーダ等)と相性が良く、低コストで効率的に間伐ができる比較的新しい方法です。形状のバリエーションとして魚骨型・放射状型などもあります。
なお、列状間伐は「部分皆伐(ぶぶんかいばつ)」といわれることもあります。
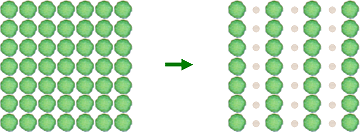
列状間伐のイメージ図
一方で、列単位で伐るため品質面の選木の自由度が下がり、優良木を含む列を伐る場合や不良木が残る場合があります。そこで、樹木の形質・形状をある程度そろえるために、定性間伐を行った上で、列状間伐を行ったり、列状間伐を行った後に、残存している不良木を取り除くために定性間伐を行うなど、列状間伐と定性間伐を組み合わせて、それぞれの間伐の長所を生かす方法で実施されることもあるようです。

列状間伐
- 長所:作業路・集材動線と一体化/機械作業に適し能率向上/コスト縮減。
- 短所:品質配慮が弱いと優良木を失う恐れ/景観への影響が目立つ場合がある。
間伐材の活用と環境効果
間伐により得られる木材は、丸太・製材・集成材・合板・CLTのほか、チップやペレット等のバイオマス燃料としても活用できます。長期利用製品として固定される炭素(カーボンストック)や、化石資材・化石燃料の代替による代替効果も期待できます。低質材でも規格外材の建材化や多段階利用(カスケード利用)を進めることで、収益と環境両面の価値を高められます。
- 選別利用:良材は構造・内装、節の多い材は下地や合板、細径木はチップ等。
- 地域循環:山側・製材・エネルギー利用を結ぶサプライチェーンを構築。
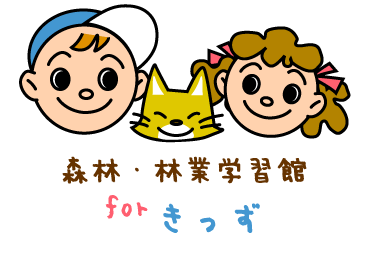
森を元気にする「間伐(かんばつ)」のお話
みなさんは森に行ったことがありますか?
森の中には、たくさんの木が生えています。でも、木が多すぎると、木どうしが場所や日光を取りあってしまい、どの木も元気に大きくなることができません。そこで行うのが「間伐(かんばつ)」です。
間伐とは、森の木を少し切って、本数を減らすこと。そうすると、残った木にたくさんの日光と栄養が届き、ぐんぐん成長できます。
間伐をすると、森の地面にも光があたり、草や小さな木が生えてきます。それが土を守り、大雨のときに土が流れるのをふせぎます。鳥やリス、虫たちにとっても、すみやすい森になります。
間伐にはいくつかのやり方があります。
定性間伐(ていせいかんばつ)
元気がない木や曲がってしまった木を選んで切る方法です。「この木は残そう、この木は切ろう」と一本ずつ見て決めます。
定量間伐(ていりょうかんばつ)
森に残す木の数をあらかじめ決めて、その割合になるように切る方法です。 たとえば「5本に1本を切る」といったやり方です。
列状間伐(れつじょうかんばつ)
木を列ごとにまとめて切る方法です。 切った場所が道になり、木を運びやすくなります。
森を守るためには、こうした間伐がとても大切です。間伐で切った木は、家を建てる材料や紙、家具、燃料など、いろいろなものに生まれ変わります。私たちの暮らしと森は、じつはとても深くつながっているのです。
〔参考文献・出典〕
林野庁・(公社)全国林業改良普及協会「間伐のしおり」/林野庁「列状間伐の手引」/林野庁「森林・林業白書」等を参照。実務は各自治体の森林計画・指針、現地条件に基づき判断。

