欅(ケヤキ、けやき)

ニレ科ケヤキ属
本州~四国~九州、朝鮮半島、中国にも分布
ケヤキ(欅)は、ニレ科ケヤキ属の落葉広葉樹。北限を青森県とし、温帯から暖帯まで広く分布する日本を代表する落葉広葉樹です「けやき」の名は「けやけき木」が由来。「けやけき」には「目立つ、ひときわすぐれている」という意味があります。ケヤキは、材としての有用性とともに、その姿の美しさも人々の心の拠りどころとなり、昔から尊ばれてきました。

茨城県だいご小学校の欅 重要文化財、推定樹齢500年

ケヤキの樹形はおうぎ形になる

孤を描くような鋸歯が特徴。葉柄は1cmほど

樹皮はまだらにはがれて、凹凸ができる

秋には赤、黄などに色づく

樹形があらわになる冬季の佇まいも美しい

ケヤキの材鑑。美しい杢を活かして家具材などに使われる
欅(ケヤキ)は日本を代表する広葉樹のひとつ
日本を代表する広葉樹といえば、ブナ、サクラ、カエデなどいくつか挙げられますが、ケヤキ〔欅〕もその一つでしょう。北海道を除いて全国的に分布しており、日本ではなじみの深い木です。早生樹とよばれるくらい成長が早く、山林だけでなく、神社や公園、住宅地、街路樹や庭園樹としても植林されており、直径が1m以上の大径材や樹高が20mにも達するものも多くみられます。ケヤキは春の芽吹きからはじまり、夏の緑陰、秋の黄葉、冬の木立と、四季を通じて美しい樹木です。
※ケヤキは北海道でも散見されますが、内地(道外)から持ち込まれた個体といわれています。

ケヤキ並木(大阪府立中之島図書館前)
ケヤキは材としての利用価値が高い

ケヤキ〔欅〕材は利用価値が高く昔から重宝されてきた
ケヤキは材質が硬く、摩耗に強い、心材が腐朽しにくいため、強靭な材「強木(つよき)」として知られていたことから、かつては「槻(つき)」と呼ばれました。木目も美しいため、利用価値が高く、古くから重宝されてきました。
大きな材は、建築材として寺社建築、城建築に使われます。また、樹齢が高く、大径になったケヤキには、しばしば、樹幹の外側にこぶ状の組織が現れ、材の繊維の配列が不規則になりいろいろな形の「杢(もく)」が現れます。これは「玉杢」とよばれ、化粧的な価値が高まり、装飾材としても珍重されます。
また、ケヤキの心材色は赤褐色で淡い赤黄色の辺材と調和して独特の風合いを醸しだします。家具、臼、杵、電柱、腕木、太鼓の胴、器具、欄間、彫刻材、椀物など様々な用途に用いられています。
鉄道林

鉄道林として植林されたケヤキ(欅)
鉄道林とは、自然災害から鉄道の線路を保護するために、鉄道沿線で自然災害が発生する可能性がある斜面や地域に植林によって設けられた森林のことで、土砂崩壊や落石、雪崩などの災害から鉄道を守る役割を果たします。鉄道林は、地すべりや土砂崩壊などの発生を抑制し、線路や列車の安全性を確保します。
特にケヤキは、鉄道林の植栽によく使用される樹種の一つです。ケヤキは成長が早く、根が強く広がる特性を持っており、岩石地や地滑りの危険がある場所でもよく育ちます。そのため、土砂崩壊や落石を防ぐ目的で斜面に植栽されることが多いです。
鉄道林は、鉄道インフラの安全性を確保するために重要な役割を果たす一方で、自然環境の保護や景観の維持にも寄与します。
清水寺の舞台の柱

清水の舞台の柱はケヤキ(欅)
清水寺の舞台は、京都東山にある有名な寺院で、その美しい風景と歴史的な価値で知られています。この舞台は、78本のケヤキの柱によって支えられています。ケヤキはその耐用年数が800年から1000年もあるといわれており、非常に丈夫な木材として知られています。そのため、お寺や神社を建築する際には、ケヤキは重要な柱材として利用されてきました。
清水寺の舞台の柱も、このケヤキの特性を活かして建設されています。舞台の柱は高さ12メートル以上にもなり、美しい景観を演出するためだけでなく、その安定性と耐久性を確保するためにも重要な役割を果たしています。ケヤキの強靭な木質は、風雨や経年劣化にも耐えることができ、長い間にわたって舞台の支えとしての機能を果たし続けることができるのです。
ケヤキの太鼓

ケヤキ(欅)の太鼓
和太鼓はその音の迫力と魅力で知られており、その音質や演奏の質には材料の選択が大きな影響を与えます。その中で、ケヤキ材は和太鼓の材料として最高とされています。ケヤキは適度な弾力と重みを持っています。この特性によって、良好な振動と音の反射を可能にし、和太鼓の響きや音色が豊かに表現されます。
また、ケヤキは木材としての強度と耐久性に優れています。和太鼓は演奏時に強い打撃を受けるため、耐久性は不可欠な要素です。ケヤキの強度はこれに応えることができ、長時間の演奏や繰り返しの使用にも耐えることができるのです。ケヤキは木目が美しく、使用年数が経つにつれて良い色つやが現れることがあります。和太鼓は演奏だけでなく視覚的にも楽しまれる楽器です。ケヤキの美しい木目が、和太鼓の外観を魅力的に彩ります。
このような特性を持つケヤキ材は、和太鼓において非常に重要な役割を果たしています。その音の響きや見た目の美しさを通じて、和太鼓は日本の伝統文化や音楽に貢献しています。
ケヤキの花と実の特徴

ケヤキは4月から5月にかけて開花し、新緑の葉とともに小さな花を咲かせます
咲く時期
4月〜5月ごろ、新しい葉が開くのとほぼ同じ時期に咲きます。
花の大きさ・色
直径は1〜2mmほどのごく小さな黄緑色〜緑色の花。葉の根元(葉腋)にかたまってつくため、葉の色にまぎれて見えにくいです。
花の種類
ケヤキは雌花(めばな)と雄花(おばな)が同じ木に咲く「雌雄同株(しゆうどうしゅ)」です。雄花は枝先の葉の下にまとまってつき、雌花は枝のやや先の方に1つずつつきます。
実(果実)
10月ごろに小さな堅果(けんか/かたい実)が熟します。翼(つばさ)のような部分があり、風に乗って遠くまで飛びます。
ケヤキの巨樹・巨木ランキング
ケヤキは、建物や家具などの材料として非常に優れているため、価値のある巨樹・巨木は次々と伐採されてしまいました。そんな中でも樹齢1000年以上のケヤキが今でも全国各地に点在しています。
| 順位 | 呼称/場所 | 幹周 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東根の大ケヤキ山形県東根市 | 15.60m | 山形県東根市 |
| 2 | 天子のケヤキ福島県猪苗代町 | 15.40m | 福島県猪苗代町 |
| 3 | 三恵の大けやき山梨県若草町 | 14.72m | 山梨県若草町 |
| 4 | 木下のケヤキ長野県箕輪町 | 12.45m | 長野県箕輪町 |
| 5 | 八幡のケヤキ福島県下郷町 | 12.00m | 福島県下郷町 |
| 6 | 野間の大けやき大阪府能勢町 | 11.95m | 大阪府能勢町 |
| 7 | 根古屋神社の大ケヤキ山梨県須玉町 | 11.90m | 山梨県須玉町 |
| 8 | 高瀬の大ケヤキ福島県会津若松市 | 11.80m | 福島県会津若松市 |
| 9 | 大六のケヤキ長野県上田市 | 11.73m | 長野県上田市 |
| 10 | 鹿島神社のケヤキ茨城県小川町 | 11.60m | 茨城県小川町 |
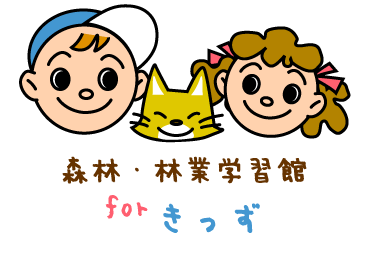
🌳 けやきってどんな木?
みなさんは、まちの中や公園で、大きくて広がった枝をもつ木を見たことがありますか?それが「けやき」という木かもしれません。けやきは、日本でとても人気のある木で、昔から人びとに大切にされてきました。
🌱 けやきのすごいところ
- とっても大きく育つ! 大きいものは高さが40メートルくらいになることもあります。ビルの10階ぶんくらいの高さです。広がった枝とたくさんの葉っぱで、夏には気持ちのいい木かげを作ってくれます。
- 四季の顔がちがう 春はやわらかな新芽、夏はあおあおとした葉、秋は赤や黄色にそまって、冬は枝の形がよく見えます。1年のうちに4回も姿を変えて楽しませてくれます。
🪵 木としてのけやき
けやきの木はとてもかたくて、長もちします。だから、昔からいろいろなものに使われてきました。
- お寺や神社の大きな柱
- 太鼓やうす(おもちをつく道具)
- 家具やドア
木の中の模様(もよう)もきれいで、職人さんが大切にしてきた木なんです。
🐦 生き物たちのたまり場
けやきの枝や葉は、鳥や虫たちにとって大事なおうちです。花がさいて実がなると、小さな鳥が食べに来て、そのタネをいろんな場所に運んでくれます。
📜 むかしからのつながり
日本のあちこちに、とても長生きしたけやきの木があります。中には1000年も生きている木も!神社の境内やまちのまんなかで、人びとの生活をずっと見守ってきました。
✨ まとめ
けやきは、大きくて美しく、たくさんの生き物や人間のくらしを支えてきた木です。もしまちで見かけたら、ちょっと立ち止まって見上げてみましょう。きっと「けやけき木(立派な木)」という名前の意味がわかるはずですよ。
〔参考文献・出典〕
茨城県教育委員会/小学館「葉で見分ける樹木」(林将之著)/新建新聞社「日本の原点シリーズ 木の文化」/学習研究社「日本の樹木」/日本文芸社「樹木図鑑」(鈴木庸夫著)/自然をつくる植物ガイド(林業土木コンサルタンツ)/日本木材総合情報センター「木ねっと」

