森林・林業が抱える課題と対策
日本の森林は国土の約7割を占め、その多くが戦後に植えられた人工林(スギやヒノキなど)です。これらは伐採して利用できる「収穫期」を迎えつつあり、木材を国産でまかなえるチャンスが広がっています。
しかし、伐採から再造林(木を伐ったあと新しく植えること)までを確実に行わなければ、森は荒れてしまいます。また、林業を持続的に経営するためには、コスト面や人材面に加え、価格形成や流通、需要の創出、花粉症対策、災害対応、デジタル化など多面的な課題があります。以下に主な課題とその対策を整理しました。
持続可能な林業経営と国産材の安定供給
木材資源を持続的に活用していくためには、〈伐る→植える(再造林)→育てる→使う〉という森林の循環を着実に回していくことが基本であるとされています。この循環を支えるためには、路網(林道・作業道)の整備や高性能林業機械の導入によって、安全性や作業の効率を高め、コストの削減を図ることが重要とされています。
また、住宅分野に加えて、学校や庁舎、店舗、オフィスといった非住宅分野においても国産材の利用を進めることで、林業生産地に適切な収益が還元され、森林資源の循環が安定的に維持されると考えられています。
課題
- 再造林の実施が十分に進まない場合、伐採後に森林が再生されず、「伐り捨て」となるリスクが生じることがある。その結果、森林資源の循環が途切れ、持続的な経営が困難になるおそれがある。
- 路網や作業機械、人材といった生産基盤が十分に整っていない状況では、作業の効率が上がらず、コストが高い水準で推移しやすく、林業経営の収益も不安定になりやすい。
対策
- 再造林や保育とあわせて、路網の整備を一体的に進めることで、伐採から再造林までの一連の流れを効率化し、森林資源の循環型経営の定着を図る。
- 高性能な林業機械の導入や更新、作業体制の見直しなどにより、安全性と生産性の両立をめざす。
- 住宅用途に限らず、学校や庁舎、店舗、工場などの非住宅建築にも国産材の利用を広げることで、木材需要を多角化し、価格の安定と地域材の価値向上につなげる。
➡ 例:CLT(直交集成板)やJAS構造材を用いた中大規模の木造建築は、炭素の貯蔵効果や工期短縮の面でも有効であり、地域材の新たな活用先として期待されています。
森林経営の集積・集約化
日本の森林は、小規模かつ分散的に所有されている場合が多く、境界が不明瞭な区域が残っています。このように所有や経営の単位が細分化されていると、施業計画の策定や作業の実施が難しくなり、結果としてコストがかさむ傾向があると指摘されています。
そのため、森林の境界を明確にし、経営の集積・集約化を進めることにより、効率的な整備や管理が可能になると考えられています。これにより、伐採・搬出・再造林といった一連の施業を切れ目なく行うことが期待されています。また、制度面では森林環境譲与税などを活用しながら、市町村や専門の担い手が連携して取り組むことが有効とされています。
課題
- 森林の所有が小規模かつ分散している場合や、所有者が不明な森林が存在する場合には、施業の計画や実施が滞りやすく、効率的な森林管理を進めるうえでの大きな障壁となることが指摘されている。
対策
- 森林の境界を明確にし、地籍整備を加速させるとともに、経営管理の委託や集約化を進める制度を円滑に運用することで、効率的な管理体制の構築を図る。
- 森林環境譲与税を戦略的に活用し、市町村の人材確保や体制整備、所有者との合意形成などの取り組みを支援する。
➡ 森林の所有を分散したままにするのではなく、一定のまとまりを持って管理していくことで、生産性の向上と再造林の着実な実施の両立が期待されます。
森林整備と災害に強い森づくり
気候変動の進行により、豪雨・台風・高温・乾燥等の極端現象が増え、山地災害や林野火災のリスクが高まっています。適切な密度管理(間伐)や再造林、治山・事前防災の計画的な実施により、土砂流出や倒木被害を抑え、“緑の防波堤”としての機能を高めます。平時の備えが被害の最小化に直結します。
課題
管理不足や気候変動の影響で、斜面崩壊・土石流・広域火災等のリスクが顕在化。
- 森林の適切な管理が行われていない地域では、立木の過密や老朽化が進み、災害に対する耐性が低下している。
- 気候変動の影響により、極端な豪雨や台風の増加が斜面崩壊や土石流の発生リスクを高めている。
- 落ち葉や倒木が堆積したまま放置されることで、山林火災が発生しやすくなり、ひとたび火災が起これば広範囲に被害が拡大するおそれがある。
対策
- 木が密集しすぎて風や雪に弱くなっている森林では、間引き(間伐)を行うことで、残された木が健全に育つよう整備する。あわせて、伐採後には新たな苗木を植える再造林を進めることで、森の回復と安定的な育成を図る。
- 急斜面や谷筋など、土砂災害の危険性が高い場所では、山腹にコンクリートブロックや丸太を組んだ構造物(山腹工)を設置したり、谷筋に砂防ダム(渓間工)を設けることで、土砂の流出や崩壊を未然に防ぐ。
- 森林火災を早期に発見するために、監視カメラやドローンなどの技術を活用し、火災発生時には地元の消防や林業関係者と連携して迅速に対応できる体制を整える。
➡ 健康に管理された森林は、大雨による土砂崩れや洪水、火災などの自然災害から人々の暮らしを守る「緑の防波堤」としての役割を果たします。
価格・流通の課題と是正(適正な価格形成)
素材生産(川上)から製材・流通(川中)、さらには建築や最終消費(川下)に至るまでのコストや品質に関する情報が十分に共有されておらず、価格転嫁が滞り、山元に収益が還元されにくい傾向にあります。こうした状況に対応するためには、実態の把握と情報の「見える化」を図り、関係者間の連携強化や契約の適正化を進めることで、安定的な取引関係を構築していくことが重要です。
課題
- 国産の木材の価格は、木材需要の増減や、円安・円高といった為替の動き、そして安価な外国産の木材との競争などの影響を受けやすく、安定しにくい状況にある。
- 素材生産者と需要者の間で、歩留まりや品質、物流に関する情報の量や精度に差(情報の非対称)があるため、価格交渉が不透明になりやすく、適正な価格がつきにくくなっている。
対策
- 作業工程ごとにかかるコストや木材の品質に関する情報を共有化・標準化を進め、合意形成を支援。
- 木材の強さなどを数値で評価する「等級付け(グレーディング)」の普及や検査体制の強化で品質評価を明確化。
- 長期・安定供給契約や地域協議会での連携を通じ、価格の下支えを図る。
➡ 情報を「見える化」して、関係者の連携強化が、適正価格と投資インセンティブの土台になる。
担い手不足と人材育成
林業分野では就業者の高齢化が進んでおり、若手人材の確保や定着が重要な課題とされています。これに対応するためには、安全教育の充実やキャリア形成の明確化、待遇の改善といった取り組みに加え、技能検定制度の活用や林業大学校などにおける体系的な学習機会の確保が有効とされています。また、女性やU・Iターン者、外国人材など多様な人材の参入を促し、「半林半X」のような柔軟な働き方を組み合わせることで、担い手の裾野を広げていくことが望まれます。
※「半林半X(はんりんはんエックス)」とは、林業ともう一つの仕事(X)を組み合わせて生計を立てる働き方を指します。
課題
危険・重労働の印象と収益不安定が、新規参入・定着の障壁となっている。
対策
- 「緑の雇用」による新規就業者の育成・定着支援、安全診断・研修の強化。
- 林業技能検定や林業大学校等を通じ、技能評価と学習機会を拡充。
- 外国人材の受け入れ環境整備と、多様な就業モデルの普及。
➡ 安全・安定・成長の見通しが、若手を惹きつける最大の要件です。
花粉症対策(スギ人工林問題)
花粉症による健康被害を軽減するためには、花粉の多くを飛散させる高齢スギを計画的に伐採し、花粉の少ない苗木への更新を進めることが有効とされています。また、伐採された木材を建築材や内装材、集成材などとして有効に活用し、〈伐る→使う→植える〉という資源循環のサイクルを経済的にも成立させていくことが望まれます。あわせて、花粉の飛散を予測する技術の高度化や、抑制技術の検証も重要な取り組みとされています。
課題
スギ人工林の高齢化・更新停滞により、花粉症の社会的損失が拡大。
対策
- 重点区域での伐採・更新、花粉の少ない苗木の増産と普及。
- 路網整備・人員確保により作業の効率化とコスト低減を実現。
- 予測モデル・抑制技術の実証と、環境影響の丁寧な検証。
➡ 花粉症対策は健康被害の緩和と林業再生を同時に進めるレバレッジ施策です。
スマート林業(デジタル化・技術革新)
ドローンやレーザー計測(LiDAR)、衛星データなどを活用して森林資源を「見える化」し、その情報を地図やクラウド上で共有することで、無駄のない施業計画を立てることが可能とされています。また、自動化や遠隔操作に対応した機械の導入や、木材のトレーサビリティを通じて需要者とデータを連携させることで、歩留まりや品質、納期の最適化が図られます。
課題
林業の現場では、作業の多くが人の経験や勘に頼って行われていることが多く、作業計画の最適化や現場での安全性、生産性の向上が思うように進まないといった課題が指摘されている。
対策
- 森林資源量の把握や木の成長予測の精度を高め、施業計画の基盤を強化する。
- GIS(地理情報システム)を活用し、路網設計や施業計画を最適化する。
- 自動化・遠隔操作・省人化に対応した林業機械を開発・導入し、安全支援システムの普及を進める。
- 伐採から加工、流通、建設までの各工程でデータを連携させ、品質・歩留まり・物流の最適化を図る。
➡ 林業のデジタル化により、現場の安全性と収益性を同時に高め、若年層の参入促進にもつながります。
木材利用の拡大とカーボン効果の見える化
木材利用の用途は、住宅に偏重する傾向から、非住宅分野や中大規模建築物へと広げていくことが求められています。あわせて、内装や什器、家具、産業資材などにも裾野を拡大していくことが望まれます。また、建物や製品に貯蔵される炭素量や、ライフサイクル全体におけるCO₂削減効果を「見える化」することにより、公共調達や民間投資における選好を高める効果が期待されています。
課題
- 住宅着工の減少で需要が伸び悩み、価格が不安定になりやすい。
- 環境価値(炭素貯蔵・代替効果)の評価が十分に伝わらない。
対策
- 公共・民間の非住宅木造化・木質化を支援し、JAS構造材・CLTの普及を促進。
- LCAに基づくCO₂削減効果の表示・評価手法を整備し、調達での活用を促す。
➡ 「使うほど環境にやさしい」を定量で示すことが、需要の質・量を押し上げます。
木質バイオマスと地域エネルギー
地域におけるエネルギーの自給や経済の循環を強化するためには、林地に残された材や未利用材の収集・搬出を効率化し、それらを発電や熱供給、木材乾燥、温室などに活用する地域内エコシステムを構築することが有効とされています。また、こうした取り組みは、丸太材の利用と競合するのではなく、相互に補完し合う形で進めることが望まれます。
課題
- 山に放置されている未利用材も多く、収集に手間やコストがかかるため、活用が進んでいない。また、収集した木材の需要先とうまくつながらず(マッチング不足)、活用が広がりにくい。
対策
- 木材の集荷から選別、粉砕、乾燥、運搬までを一体的に整備し、熱利用拠点(温浴施設や乾燥施設など)を地域に整えることで、効率よく使える仕組みを創出する。
- 製材工場や木材乾燥施設、温浴施設、公共施設などの熱需要と、バイオマスの供給を結びつける地域モデルを広げる。
➡ 木質バイオマスは、これまで使われていなかった森林資源に新たな価値を持たせ、エネルギーとしても活用できる可能性を持っています。
輸出と合法性確認(クリーンウッド)
木材需要の多角化を図る取り組みの一環として、輸出の拡大が重要視されています。海外の規格や認証への適合を進めるとともに、強度等級付け(グレーディング)に対応できる人材の育成や検査体制の整備を通じて、品質と信頼性の向上が求められます。また、違法伐採対策として、国内ではクリーンウッド制度に基づく合法性確認の徹底が進められており、サプライチェーン全体の信頼性を高めることが期待されています。
課題
- 規格・品質・表示の不一致や検査・証明の負担が輸出の壁となる。
- 合法性確認の未整備は、国内外の信用を損ねるリスク。
対策
- 海外規格対応の技術検証・認証取得支援、グレーダー育成、検査機関連携。
- 合法性確認研修・相談体制・情報発信の強化で市場の信頼性を高める。
➡ 品質・規格・合法性の「三位一体」で、日本産材の国際競争力を高めます。
山村地域の活性化
森林は木材の供給にとどまらず、食や工芸、観光、教育、健康など、多面的な価値を有するとされています。こうした価値を活かすためには、里山の整備や獣害対策、特用林産物の振興に加え、都市企業やNPOとの協働、「半林半X ※」といった柔軟な働き方の普及が重要とされています。これにより、地域の暮らしと仕事の選択肢が広がり、定住人口や関係人口の増加につながることが期待されています。
課題
人口減少・高齢化により、山村の担い手とサービスが縮小し、地域内経済が痩せる。
対策
- NPO・自伐型等が主体の里山整備と森林空間サービスの展開を支援。
- 獣害対策とバイオマスの地域利用で、暮らしの安全と自立性を高める。
- 特用林産物(しいたけ、山菜、漆等)や林産文化の継承・ブランド化。
➡ 森と暮らしを結び直すことが、地域の経済・文化・福祉を底上げします。
林業の課題と対策の要点
森林は木材の供給源であると同時に、国土の保全や生物多様性の確保、気候変動への対応、さらには文化の継承といった多面的な機能を担っているとされています。現在の課題としては、再造林の徹底や森林経営の集積・集約化、価格や流通の是正、人材確保と安全対策、花粉症対策、災害への備え、デジタル技術の活用、木材需要の拡大、バイオマス利用の促進、木材輸出や合法性確認の強化など、相互に関係し合う多くの要素が挙げられます。
これらの施策をパッケージとして総合的に推進し、「伐る→植える→育てる→使う」という森林資源の循環を着実に回していくことが、持続可能な森林・林業の実現に向けた近道とされています。また、私たち一人ひとりも、「国産材を選ぶ」「森林に関心を持つ」といった日々の行動を通じて、この循環を支える担い手になることができます。
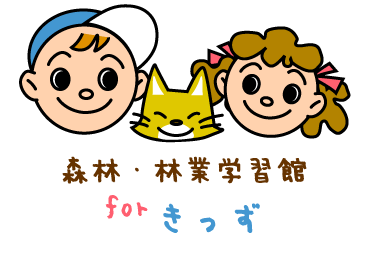
森のなやみとみんなでできること
日本の森は国土の約7割をしめています。スギやヒノキなどの人工林(人が植えた森)は、ちょうど「使いどき」をむかえています。でも、木を伐ったあとに新しく苗木を植える再造林(さいぞうりん)が追いつかないと、森がよわってしまいます。
また、森の持ち主がたくさん分かれていて手入れができない場所もあります。大雨や台風で山くずれや洪水がおきやすくなったり、スギ花粉で花粉症に悩む人がふえたり、山で働く人が少なくなったりと、いろいろな問題が出てきています。
そこで大切なのは「森を元気にする行動」です。たとえば、間伐(木を間引くこと)で残った木を健康に育てること、災害をふせぐために治山(ちさん)工事をすること、花粉の少ない苗木に植えかえること、ドローンやレーザーで森を調べるスマート林業など、新しい方法も使われています。
私たちにできることもあります。国産の木で作られたえんぴつやノートを選ぶ、木のものを長く大切に使う、植樹体験に参加するなど、小さな行動が未来の森を守ります。森は空気や水をきれいにし、たくさんの生き物を育てる大切な場所。みんなで守り育てていきましょう。
〔参考文献・出典〕
林野庁「森林・林業基本計画」/林野庁「令和8年度林野庁予算概算要求の概要」/内閣官房「第1次国土強靱化実施中期計画」等

