再植林 (Reforestation)
森林を「機能」とともに取り戻す
再植林は、伐採や災害、土地利用の転換などで失われた森林を、計画的に「機能ごと」回復させる取り組みです。単に木を植えるのではなく、CO₂吸収、防災、生物多様性、木材生産といった目的に応じて「何を・どこに・どう植えるか」を設計します。
京都議定書における再植林の定義
「再植林」とは、かつて森林だった土地が別の用途(農地・放牧地など)に使われた後に、再び森林へ戻すために木を植えることを指します。 国際的なルールである京都議定書では、再植林は「1989年12月31日時点で森林ではなかった土地に、1990年以降に行われた植林」と定義されています。
これは、温室効果ガスの削減努力として森林を新たに再生した活動を明確にするためのもので、地球温暖化対策としての森林の役割が重視された背景があります。
※なお、「新規植林(Afforestation)」は長い間森林でなかった場所に初めて森林をつくることで、再植林とは区別されています。
再植林が行われる主なケース
| 状況 | 具体的な対応 | 目的・機能 |
|---|---|---|
| 木を伐採した後の森林再生 | 伐った跡地に苗木を一定の間隔で植え、下草刈りや間伐を行いながら育てていく | 持続的な木材生産、CO₂の吸収回復 |
| 台風・豪雨・山火事などの被害地 | 倒木処理のあと、雨風に強い木を組み合わせて植え、土砂流出を防ぐ | 防災・減災、山の保水力の回復 |
| 昔の農地や放牧地など | 地力を戻したあと、先に育ちやすい広葉樹を植えてから針葉樹を導入 | 景観の再生、生態系の復元 |
再植林のポイント──目的に応じた森づくり
1. 樹木の種類を選ぶ
地域の気候や土の性質、日当たりなどに合わせて、複数の種類の木(混交林)を植えることで、自然災害や病害虫に強い森をつくります。
例:風の強い場所ではアカマツとコナラ、土砂災害の心配がある場所ではカエデやヤマザクラを組み合わせるなど。
2. 木の配置を工夫する
同じ木を一列に並べず、筋状やかたまりごとに配置することで、風や病気の広がりを防ぎやすくなります。川沿いには広葉樹を植えて水辺を守ることもあります。
3. 手入れを計画的に行う
木を植えたあとは、下草刈りやツルの除去を1~5年間続け、木がしっかり育つようにします。その後、密集してきた木を間引く「間伐」を10~20年後に行い、光や空間を整えます。
再植林の課題と対策
- シカやイノシシによる食害:苗木を守るためにネットや柵を設置し、好まれにくい木を選ぶこともあります。
- 干ばつ・気候の変化:地表の乾燥を防ぐマルチングや、植える時期の調整などが行われます。
- 単一樹種のリスク:病害虫や環境の変化に強くするために、いろいろな木を混ぜて植える工夫が必要です。
- 人手不足:機械やドローンの活用、ボランティアの協力、作業道の整備によって効率化を図ります。
- 費用の確保:森林環境譲与税や国の補助金、企業の支援などを活用して再植林を進めています。
再植林の効果をどう測るか
- 初期生残率:苗木を植えて1~2年後に、どれだけの木が枯れずに残っているかを確認します(目標は80%以上)。
- 被覆の完了:木の枝葉が広がって地面をおおう「林冠閉鎖」が起これば、下草刈りは不要になります。
- 森の機能の回復:CO₂の吸収量、土砂の流出量の減少、生き物の種類などから、再植林の成果を確認します。
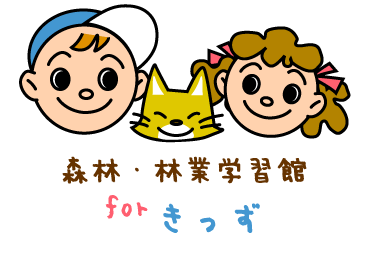
森をもういちど育てるおしごと「再植林」ってなに?
強い風や大雨、火事やきこりのしごとで木が少なくなった場所に、もういちど木を植えて森を作りなおすことを「再植林(さいしょくりん)」というよ。
どうして再植林がひつようなの?
- くらしを守るため:森は雨をゆっくりためて洪水をふせいだり、土砂くずれをふせぐバリアになる。
- 生きものの家づくり:鳥や虫、動物たちのすみかがもどってくる。
- 地球のため:木が大きくなるあいだ、空気中のCO₂をすいこんでくれる。
どんなふうにやるの?
- 山の土をととのえる(石や切り株をどかして、苗木が育ちやすくする)。
- 小さな苗木をやさしく植える(根っこがひろがるように穴をほる)。
- 草に負けないように草をかる、つるを切る(これを「下草刈り」っていう)。
- 大きくなってきたら込み合った木を少し減らして、光をわけあう(「間伐」)。
はじめの1~2年が、とくに大事。シカに食べられないようにネットでまもることもあるよ。
森はすぐには大きくならないけれど、みんなで手をかければ、くらしを守る「みどりの防波堤」になってくれるよ。
〔参考文献・出典〕
IPCC GPG LULUCF/UNFCCC関連文書、林野庁・環境省の各種資料

