CDM(クリーン開発メカニズム)植林 しーでぃーえむくりーんかいはつめかにずむしょくりん
先進国と途上国が協力して進める温室効果ガス削減の仕組み
CDM(クリーン開発メカニズム)植林とは、先進国と開発途上国が共同で植林などの吸収源事業を実施し、開発途上国の持続可能な開発に貢献するとともに、その事業によって吸収された温室効果ガスの量(吸収分)を、先進国が自国の削減目標の達成に利用できる制度です。京都議定書で定められた「京都メカニズム」の一形態です。
京都メカニズムにおける位置づけ
京都メカニズムとは、1997年に採択された京都議定書で導入された国際的な仕組みで、地球全体で温室効果ガスの排出削減を効率的に進めるための制度です。その中には、共同実施(JI)、排出量取引(ET)、そしてクリーン開発メカニズム(CDM)の3つがあります。CDMはその中でも、先進国と開発途上国の協力によって排出削減・吸収活動を行う仕組みで、植林事業はその代表的な例です。
植林CDMのしくみ
CDM植林では、開発途上国の森林減少地や荒廃地などに苗木を植え、森林を再生させることで大気中の二酸化炭素(CO₂)を吸収します。これにより得られた「吸収量」は、国際的な基準に基づいて算定・認証され、先進国の温室効果ガス削減目標の達成に利用されます。一方で、現地では雇用創出や土壌保全、水源涵養などの効果も期待され、地域社会の持続可能な発展に寄与します。
主な実施例
- インドネシア: スギ・アカシアなどの植林による荒廃地の再生事業。日本企業や国際機関が協力。
- 中国・雲南省: 放牧地を森林化する再造林プロジェクト。地域住民の参加型で実施。
- インド: 村落単位での混交林造成による二酸化炭素吸収と生活環境改善。
- ラテンアメリカ諸国: メキシコ・コスタリカなどで、熱帯林の再生やカーボンクレジット事業として展開。
意義と課題
CDM植林は、地球温暖化対策とともに、森林の回復や地域経済の向上にもつながる点で意義があります。一方で、長期的なモニタリングの必要性、土地利用権の整理、クレジット算定の複雑さなどの課題も指摘されています。これらを踏まえ、近年はパリ協定下での新しい枠組み(Article 6.4メカニズム)への移行が進められています。
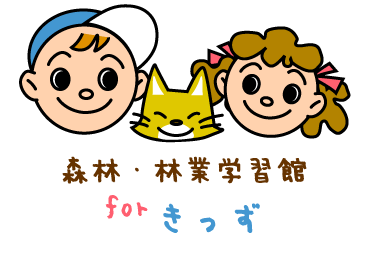
🌏 森づくりで世界を助けるしくみ「CDM」ってなあに?
みなさんは、世界の国どうしが力を合わせて「地球を守る森づくり」をしていることを知っていますか? そのしくみのひとつが「CDM(クリーン開発メカニズム)」です。
CDMでは、お金や技術のある国(先進国)と、森を増やしたい国(開発途上国)がいっしょに協力して植林を行います。たとえば、荒れた土地に木を植えて新しい森をつくり、木が成長して二酸化炭素を吸い取ってくれると、その分だけ地球の温暖化を防ぐことができます。
植林を手伝った先進国は、その森が吸い取った二酸化炭素の量を「自分の国のがんばり」として数えることができます。つまり、森をふやすことが、地球を冷やすことにもなるのです。
CDMの植林は、ただ木を植えるだけではありません。そこに住む人たちの仕事をふやしたり、水や土を守ったりと、地域の暮らしをよくすることにも役立ちます。森を育てることが、世界の人々と地球の未来を助けることにつながっているんですね。

