里山 さとやま
人の暮らしと自然が共存する山や森
里山(さとやま)とは、日本の農村地帯に見られる「人の暮らしと自然が共存する山や森」のことをいいます。昔から日本では、村の近くの山(=里山)を、薪(まき)や炭をとる場所、落ち葉を堆肥に使う場所、きのこや山菜を採る場所などとして活用してきました。つまり、里山は「自然そのまま」ではなく、人の手が加わって維持されてきた自然環境です。

里山の風景(井仁の棚田|広島県)
里山(さとやま)とは?
里山とは、人々が暮らす村や畑の近くにある山や森のことで、昔から人の手が加わりながら大切に使われてきた自然です。たとえば、木を燃料にしたり、落ち葉を畑の肥料にしたり、山菜やキノコを採ったりと、生活に役立つものを得る場所でした。
そうした利用や手入れが長い間続けられてきたことで、森・草地・水辺などさまざまな自然が入り混じるような環境ができあがり、多くの生き物がすめる豊かな場所になっているのが特徴です。
奥山(おくやま)との違い
里山とよく比べられる言葉に「奥山」があります。奥山とは、人があまり入らず、村から離れた深い山のことを指します。
奥山は手つかずの自然が多く、動物のすみかや水をたくわえる場所としての役割があります。それに対して里山は、薪や農業などに使われることを前提に、人の暮らしと自然が一緒に成り立つように手入れされてきた場所です。
- 里山:人里に近い/人が手入れして利用する/さまざまな自然が混ざり合っている
- 奥山:人があまり入らない/自然にまかせたまま/野生動物や水源を守る場所
これらの言葉の使い方は地域によって少し違いがあります。おおまかには「人の手が入っているかどうか」や「人里からの距離感」で区別されると考えるとわかりやすいです。
里山が大切な理由
- 生物多様性:手入れの入った林縁・草地・水辺など、ニッチが豊富で多様な種が共存しやすい。
- 防災・環境保全:土砂流出抑制や水源涵養、ヒートアイランド緩和、炭素貯留などに寄与。
- 文化・景観:薪炭利用、落ち葉掃き、里祭り、里道・水路管理など、地域の伝統知の母体。
- 教育・健康:自然体験・環境学習・地域コミュニティづくりのフィールド。
里山の歴史と利用
近代以前、里山は燃料(薪・炭)や肥料、建築・生活資材の供給場所でした。木を切って薪にしたり、炭を作ったり、畑にまく肥料を落ち葉から作ったり、建物の材料にしたりと、暮らしに欠かせない存在でした。
伐採→萌芽更新(株立ち)→再利用という循環利用が基本で、定期的な手入れが景観と生態系を保ってきました。しかし、戦後には、電気やガスが使われるようになり(エネルギー転換)や生活の変化により里山の利用が減ると、手入れがされないまま放置され、樹種構成や林相が大きく変わった地域も少なくありません。
今の里山がかかえる問題
- 管理放棄・担い手不足:木が増えすぎたり暗くなったりして、生き物がすみにくくなっています。植生の単純化・過密化、林床の暗化、景観・生態機能の低下しています。
- 獣害の増加:シカやイノシシが田畑を荒らしたり、森の生態系を変えてしまったりしています。奥山と里の境界が曖昧になり、動物による農林業被害・生態系改変が拡大しています。
- 土地利用の変化:使われなくなった土地が増えており、田畑の放棄や空き家、池や水路の管理不足などが進んでいます。耕作放棄地・空き家の増加、ため池・水路の機能が低下しています。
- 気候変動リスク:大雨や暑さ、乾燥による山の崩れや火災などのリスクも高まっています。極端降雨・高温・乾燥化による土砂災害・林野火災リスクの顕在化しています。
里山を守り活かすために
- 定期的な手入れ:木を間引いたり、草を刈ったり、水路を掃除したりすることが大切です。
- 地域の中で使う仕組みづくり:薪や竹を使ったり、地元でとれた木材を活かしたりする方法もあります。
- 動物との付き合い方:電気柵などの対策とあわせて、森と里の境をきちんと管理します。
- みんなで参加する:学校や地域、ボランティアなどが協力して守っていくことが大切です。
- 防災にも役立てる:山や川の整備を進めることで、災害にも強い地域を目指せます。
よく出てくる言葉
- 雑木林・二次林:いろんな種類の木が混ざっている森。人が手入れをして再び育てた林です。
- 里地・里川:田畑や水路など、里山と一緒に使われてきた自然の場所です。
- 里海:人の暮らしに近い海辺。漁や干潟などがあり、山とつながる自然です。
- モザイク環境:森、草地、水辺などがパッチワークのように交じり合っている自然のことです。
里山は、人が関わることで豊かさが保たれてきた半自然の空間です。奥山の大きな生態系と連続しつつ、私たちの生活圏に最も近い自然として、多面的な価値を提供します。放っておけば失われ、手を入れれば再生する 自然と上手につきあいながら、次の世代にも引きついでいくことが、今の私たちにできる大切なことです。
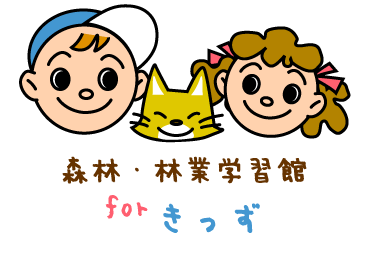
🌳 里山ってなあに?
〜人と森がなかよしの場所〜
みんなの家の近くに、ちょっとした森や山があるのを見たことはあるかな?
それが「里山(さとやま)」とよばれる場所かもしれないよ。
昔から日本では、山や森をただの自然として見るだけじゃなく、生活の一部として使っていたんだ。
たとえば、火をたくときの薪(まき)を山からとってきたり、落ち葉を畑の肥料にしたり、山菜をとったりしてね。
🐿️ どうして生き物がたくさんいるの?
里山では、いろんな自然がごちゃまぜになっているんだ。
たとえば…
- 木がたくさんある森
- 草がいっぱいの草地
- 小さな池や流れる水路
- 畑や田んぼ
これらがちかくにあることで、たくさんの生き物が、それぞれに合った場所でくらすことができるんだよ。
こういうのを「モザイクみたいな環境」って言ったりするよ。
🏡 人が森に入るっていいことなの?
「森はさわらないほうがいい」と思うかもしれないけど、里山では人がていねいに手入れをすることで、自然が元気になることもあるんだ。
たとえば、草がのびすぎたら刈ったり、木がこみ合いすぎたら少し切ったりすると、光が入って、植物も動物もすみやすくなるよ。
🦌 今はちょっとたいへん…
でも今は、昔のように里山を使う人が少なくなって、草や木がのびすぎたり、動物が田んぼに入ってきたりして、ちょっと困っていることもあるんだ。
🤝 ぼくたち・わたしたちにできること
- 里山にある植物や生き物をよく見てみよう
- ごみをすてない、道をこわさないなど、やさしい行動をしよう
- 自然体験やボランティアに参加してみよう
森はこわいところじゃなくて、人と仲よくできるパートナーなんだよ。
🌱 まとめ
里山は、「自然」と「人のくらし」がいっしょに育ってきた場所。
ただの山じゃなくて、人が森を大切にしながら使ってきた、日本ならではの自然なんだ。
これからもみんなで見守っていけたらいいね!

