照葉樹 しょうようじゅ
暖温帯〜亜熱帯に発達する常緑広葉樹
照葉樹とは、暖温帯から亜熱帯にかけて発達する常緑広葉樹の一群で、日本では本州の関東南部以西、四国、九州、南西諸島などの温暖で湿潤な地域に多く分布しています。
その名のとおり、葉は深緑色で革質(厚くて堅い質感)をもち、葉の表面には「クチクラ層」と呼ばれるロウ状の層があるため、光沢があり“照るように見える”のが特徴です。このクチクラ層は、水分の蒸発を抑えたり、寒さや強い日差しから葉を守ったりする役割があるとされています。

ドングリをつけた秋のアラカシ(写真:PhotoAC)
照葉樹と硬葉樹
照葉樹林は夏も冬も葉を落とさない常緑樹で構成されており、年間を通じて緑豊かな森を形づくります。森林の内部はやや薄暗く、常緑の下層木やシダ、苔類などが多く見られる湿潤な環境となります。
さらに、熱帯の照葉樹では葉がより硬くなる傾向があり、これらはとくに「硬葉樹(こうようじゅ)」と呼ばれることもあります。これは、より強い日差しや乾燥から葉を保護するための適応とされています。
照葉樹の種類
日本における代表的な照葉樹には以下のような種があります。
- カシ類(アラカシ、ウラジロガシなど)
- シイ類(スダジイ、ツブラジイ)
- クスノキ(樟)
- タブノキ(椨)
- モチノキ
- モッコク
- ヤブツバキ
- ハイノキ
- ヤブコウジ
- タイミンタチバナ
- カゴノキ
- シロダモ
など
これらの照葉樹は、材としての利用価値もあるほか、神社の御神木や庭木、街路樹などとしても親しまれています。また、ドングリなどの果実は動物の重要な食料源でもあり、生態系の中で大切な役割を担っています。
照葉樹林文化圏
照葉樹林は日本だけでなく、中国南部や台湾、ヒマラヤ山麓、東南アジアなどにも広く分布しています。これらの地域には、温暖で湿潤な気候に適応した常緑広葉樹の森(照葉樹林)が広がっており、同じような自然環境のもとで暮らしてきた人々は、類似した農耕・生活の文化を育んできました。
たとえば、山間地の焼畑農耕(焼いて土地を肥やし、一定期間作物を育てる方法)や、お茶やアワ・ヒエなどの作物を栽培する農業文化、漬物や発酵食品などを用いた保存食の知恵、樹木や竹を使った生活道具の利用などが挙げられます。これらは、日本の里山文化と共通する特徴でもあります。
こうした共通性から、学術的にはこれらの地域をまとめて「照葉樹林文化圏」と呼ぶことがあります。つまり、「似た森のある場所では、似た文化が育ちやすい」という考え方に基づき、自然環境と人間の暮らしの深い関わりが注目されているのです。
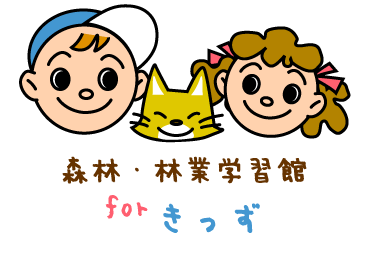
🌿 てかてか光る?
照葉樹(しょうようじゅ)ってなに?
森の中で、葉っぱがつやつや光って見える木を見たことはありますか?それは、もしかしたら「照葉樹(しょうようじゅ)」かもしれません🌟。
照葉樹は、1年中ずっと葉っぱがしげっている常緑樹(じょうりょくじゅ)の仲間です。葉っぱは厚くてかたい「かわのような」手ざわりで、表面はロウのようなつるつるしたクチクラ層におおわれています。そのおかげで、つやつや光って見えるんだね✨。
🌳 どんな木があるの?
日本では、カシ、シイ、クスノキ、ヤブツバキなどが照葉樹の仲間です。みんな名前を聞いたことがあるかな?どれもあたたかい地方に生えていて、木の実や花もたくさんつけます。
🌏 ほかの国にもあるの?
実は照葉樹の森は、日本だけじゃなくて、中国南部や台湾、ヒマラヤのまわり、東南アジアにも広がっています。あたたかくて雨がたくさんふる場所にぴったりなんだね。
👩🌾 森と人のくらし
おどろくことに、こういう森にすんでいる人たちは、にている文化(ぶんか)をもっているんです。たとえば、焼きはた農業(やいて畑をつくる方法)、お茶をのむ習かん、山のめぐみを使った発酵食品など、いろいろな共通点があるよ!
このことから、学者の人たちは「照葉樹林文化圏(しょうようじゅりんぶんかけん)」という言葉を使って、「似た森のある場所では、似た文化が育ちやすい」と考えています🌱。
🦌 どうぶつたちのすみかにも
照葉樹の森は、いろんな生きもののすみかにもなっています。ドングリをたべるイノシシやシカ、木の実をひろうリスや鳥などが、森のめぐみをもらって生きているんだよ。
🌲 さいごに
つやつや光る葉っぱの照葉樹は、自然の中でとっても大事な木なんだね🌿。森を歩くときは、どんな葉っぱがあるか、ぜひじっくり見てみてください👀✨。
〔参考文献・出典〕
長崎の樹木「豆知識」

