在来軸組工法 ざいらいじくぐみこうほう
伝統が息づく、日本の合理的木造構法
在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう)は、日本に昔から伝わる伝統的な木造建築の工法です。柱や梁(はり)、桁(けた)、土台といった“骨組み”を木材で組み上げて家を建てる構造で、「木造軸組工法」とも呼ばれています。
この方法は、長い歴史の中で発展してきた日本独自の建築スタイルで、特に和風建築との相性がよく、今でも多くの住宅で採用されています。設計の自由度が高く、間取りの変更や増改築にも柔軟に対応できるのが特長です。
ちなみに「在来」とは、「昔からある」「もともとの」という意味。つまり「在来軸組工法」とは、日本で古くから使われてきた木の骨組みによる家づくりの技術を指す言葉です。

在来軸組工法|伝統が息づく、日本の合理的木造構法
在来軸組工法と在来軸組構法の違い
「在来軸組工法」に対し、「在来軸組構法」という用語もあります。どちらも「日本の伝統的な木造建築の流れを汲む、柱や梁などで骨組みを構成する建築方法」ですが、工法は、実務的・施工的な用語で、建築学的・構造設計的な用語として使われています。
「工法」は、建物をどうやって施工するかという施工手順や工程、作業方法、技術を指し、構法は、建物をどのような構造で成立させるかという構造的なしくみ・理論・技術体系を指して使われるケースが多いようです。
なお、在来軸組工法は、「木造軸組工法」の他、「在来工法」「在来木造」「木造軸組」などと呼ばれることもあります。
在来軸組工法の歴史
奈良時代〜平安時代(8〜12世紀)
在来軸組工法の起源は、奈良時代から平安時代にさかのぼります。仏教の伝来とともに中国や朝鮮半島の建築技術が伝わり、日本にも木造建築の基礎となる軸組構造が導入されました。法隆寺などの古代寺院に見られるように、柱と梁を組み合わせて建物を支える構造は、この時代からすでに確立されていたのです。これらの建築物は、日本の気候や風土に合わせて徐々に変化を遂げながら、日本独自の木造建築文化の礎を築いていきました。
鎌倉〜室町時代(13〜16世紀)
鎌倉時代から室町時代にかけては、寺院や神社、城郭の建設が盛んになり、木造建築に関する技術も一層発展します。この頃、大工職人たちは「継手(つぎて)」や「仕口(しぐち)」といった、木材同士を金物を使わずに巧みに接合する技術を発展させました。これらの技法は、構造的な強度だけでなく、美しさや機能性も追求されており、現代の在来工法の技術的な基盤となっています。
江戸時代(17〜19世紀)
江戸時代に入ると、武家屋敷や町家、農村の民家といった一般住宅にも軸組工法が広く普及しました。この時期、各地の気候や生活文化に応じて、さまざまな地域独自の建築様式が生まれ、在来工法は「地域色」を持つようになります。たとえば、豪雪地帯では屋根勾配を工夫したり、京都では細長い敷地に対応した「京町家」が生まれるなど、木造住宅の多様性が花開いた時代といえるでしょう。
明治〜昭和前期(19〜20世紀前半)
明治から昭和の初期にかけては、西洋建築の技術が急速に導入され、鉄骨やコンクリート造の建物が都市部を中心に建てられるようになります。しかし、住宅建築においては依然として木造の在来工法が主流であり、特に地方では変わらず大工の手による建築が続けられました。この時代になると、設計図面の導入や構造計算の技術も発展し、伝統的な工法に近代建築技術が融合しはじめます。
昭和後期〜平成(20世紀後半)
戦後の高度経済成長期には、プレハブ住宅やツーバイフォー工法といった新しい住宅建築手法が台頭しますが、在来軸組工法もまた進化を続けます。1970年代以降は建築基準法の改正などによって耐震性が求められるようになり、筋交い(すじかい)や金物接合の強化など、現代の耐震設計が導入されていきました。さらに、プレカット技術(工場での木材加工)の普及により、品質の安定と工期の短縮が図られるようになります。
現代(令和時代)
そして現代においては、省エネ性能や耐久性、バリアフリー設計など、多様なニーズに応えるべく、在来工法もさらに改良が進められています。また、スギやヒノキといった国産材を使いやすい工法であることから、地域林業との連携や国産材利用促進といった観点でも再評価されています。加えて、空き家のリノベーション(※)や古民家再生の現場でも、その構造の柔軟性が活かされており、過去と未来をつなぐ建築工法としての価値が見直されつつあります。
※既存の建築物に大規模な改修工事を行い、機能や価値を向上させる「刷新」や「修復」のこと
仕組みと構造
在来軸組工法は、柱・梁・桁・筋交いなどを組み合わせた「軸組(骨組み)」で建物を構成する、日本の伝統的な木造建築工法です。各部材にはそれぞれ明確な役割があり、全体でバランスよく荷重や揺れに耐える構造になっています。
■ 柱(はしら)
建物の垂直方向の構造の中心を担う重要な部材。基礎から屋根まで通して立ち、上からの荷重(屋根や2階の重み)を地面に伝える役割を果たします。通常、四隅や壁の取り合い、主要な間仕切り部分などに配置されます。
■ 梁(はり)
柱と柱を水平方向につなぐ構造材で、上からの荷重を分散して柱へと伝えます。1階と2階の床や、屋根を支える部分に使われ、たわみや曲がりに対して強い材が選ばれます。
■ 桁(けた)
梁と似た構造材で、建物の長手方向に配置される横架材です。主に屋根を支える部材で、梁と桁が一体となって「梁桁構造」を構成します。古くから日本建築で使われてきた構造です。
■ 土台(どだい)
柱の下部に横向きに配置され、基礎と柱をつなぐ構造材です。建物の一番下にあり、基礎からの力を柱に伝え、また湿気やシロアリから柱を守るためにも重要な役割を担います。防腐処理された材が使用されることが一般的です。
※基礎は、建物の一番下にあるコンクリート部分で、建物全体の重さを地面に伝える役割を担っています。地盤に直接接しており、家を支える土台そのものです。土台は、基礎の上に乗る最初の木材で、柱や壁を支える構造材です。コンクリートと木造のつなぎ役として重要です。
■ 筋交い(すじかい)
柱と柱の間に斜めに入れる補強材で、地震や台風などの横からの力(水平力)に対する耐性を高めるために不可欠です。壁の中に設置され、建物の「ねじれ」や「ゆがみ」を防ぎます。
■ 火打ち梁(ひうちはり)・火打ち土台
梁や土台の直角を保つための斜め材で、直角部分の変形やねじれを防ぐために使われます。とくに地震時などに構造を安定させるための補助材です。
■ 間柱(まばしら)
構造上の主要な柱の間に入れる小さな柱状の部材で、壁の下地を支える役割を担います。間仕切り壁などに使われ、石膏ボードや外壁材を貼るための下地として活用されます。
■ 羽子板(はごいた)ボルト・ホールダウン金物
近年では構造の強度向上のために金物補強も多く用いられます。羽子板ボルトは梁と柱をしっかり固定し、ホールダウン金物は柱が地震で抜けるのを防ぐための重要なパーツです。
このように、在来軸組工法は「柱」「梁」「桁」「土台」などの軸となる構造部材を立体的に組み上げることで、建物全体の強度を保っています。さらに、筋交いや金物補強によって横揺れや地震にも対応する形に進化しています。
「在来(ざいらい)」は昔ながらの日本の建築方法、「軸組(じくぐみ)」は柱や梁で骨組みを作ること。その名の通り、伝統と合理性を兼ね備えた構法です。
※「在来(ざいらい)」= 昔ながらの方法で「軸組(じくぐみ)」= 柱や梁を組む という意味で、「在来軸組工法」と呼びます。
在来軸組工法のメリット
在来軸組工法の大きな特長は、柱と梁で建物を支える「軸組構造」であることです。この構造のおかげで、壁に頼らずに建物の強度を確保できるため、間取りの自由度が高く、将来的なリフォームや増改築も柔軟に対応できます。
また、使用する木材が通気性に優れているため、家全体が呼吸しやすく、湿気がこもりにくい構造になっています。このため、カビの発生を抑えたり、木材の腐朽を防いだりと、住まいの健康維持にも貢献します。
さらに、在来工法は長い歴史の中で日本各地に根付いており、地域の気候や風土に適した設計がしやすいという特性もあります。たとえば、積雪地帯や高温多湿な地域など、さまざまな環境に対応した柔軟な建築が可能です。
在来軸組工法のデメリット
在来軸組工法は、伝統的な技術を活かした柔軟性の高い工法である一方、職人の手作業が多く、熟練の技術が求められる工法でもあります。そのため、大工の技術力や経験によって、建物の仕上がりや品質に差が出やすいという点が課題です。
また、柱や梁などの構造材を現場で加工・組み立てる工程が多いため、プレハブ工法やツーバイフォー工法に比べて工期が長くなる傾向があり、天候の影響を受けやすい点も留意すべきポイントです。
さらに、耐震性能についても設計や施工の精度によってばらつきが出やすく、十分な耐震性を確保するには、設計段階からの入念な計画と、信頼できる施工が不可欠です
在来工法は、間取りやデザインの自由度が高い反面、現場での作業が多く、木材の品質や扱い方、さらには施主の要望を細部まで反映させるための調整が複雑になります。このような事情から、施工する側には高い対応力や判断力が求められ、施工実績が豊富で信頼のおける業者の選定が極めて重要となります。
近年では、こうした課題を克服するために、木材をあらかじめ工場で加工する「プレカット加工」や、在来工法をベースにした現代的な技術(高耐震パネル・金物工法など)を導入する工務店も増加しており、伝統の強みを活かしながら品質の安定化が図られつつあります。
在来工法とプレハブ工法の違い
日本で採用されている工法として、プレハブ工法もあります。これは部材やユニット(壁・床・天井など)を工場であらかじめ生産し、現場では主に組み立てで完成させる方式で、在来軸組工法との違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 在来軸組工法(木造軸組) | プレハブ工法 |
|---|---|---|
| 構造の基本 | 柱・梁で荷重を受ける「軸構造」。筋交い等で水平力に抵抗。 | 壁・床・天井のパネルやユニットによる「面構造」やボックス構造。 |
| 部材の製作 | 主に現場で加工・調整(近年はプレカット活用も)。 | 工場で高精度に量産・品質を安定化。 |
| 施工の流れ | 現場で墨出し→建て方→合板・耐力壁→造作など工程が多い。 | 工場製パネル・ユニットを現場で組み立て、工程が簡素。 |
| 設計自由度 | 高い。間取り・開口計画・増改築の柔軟性に優れる。 | 規格に合わせるため自由度は相対的に低め。 |
| 工期 | やや長め(天候や現場調整の影響を受けやすい)。 | 短め(現場は組立中心で天候影響が小さい)。 |
| 品質のばらつき | 職人の技量・現場条件による差が出やすい。 | 工場管理で均質化しやすい。 |
| 耐震・耐火・気密 | 設計・施工次第。金物工法や耐力壁採用で高性能化可能。 | パネル化により気密・断熱・耐震・耐火を確保しやすい。 |
| リフォーム適性 | 良好。構造と間仕切りを分けやすく改修しやすい。 | 構造壁の制約により間取り変更は制限されがち。 |
| 地域材・意匠 | 地域材(スギ・ヒノキ等)や和の意匠を取り入れやすい。 | 規格化重視で地域材・細部意匠の自由度は限定的。 |
| コスト感 | 設計・仕様・職人手配で上下。オーダー性が高い。 | 量産・標準化でコストを抑えやすい。 |
| 適するニーズ | 自由設計・将来改修・地域材活用・意匠重視。 | 短工期・一定品質・コスト最適化・標準仕様。 |
※どちらが優れているかは一概に決められず、求める自由度・工期・コスト・品質安定性・将来の改修計画などの優先順位で選択が異なります。
在来軸組工法とツーバイフォー工法の違い
日本で採用されている木造住宅の工法として、ツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)があります。これは、 主に2インチ×4インチ(約50mm×100mm)の角材で枠組みが作られることに由来しており、この枠組みと合板で構成された壁・床・屋根の「面(六面体の箱)」が、建物にかかる荷重を分散して支えます。柱と梁で骨組みを作る在来軸組工法とは構造思想が異なります。端的に言えば、ツーバイフォー工法は、壁や床といった「面」で建物を支えるのに対し、在来軸組工法は「線」で支えます。両者の主な違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 在来軸組工法(木造軸組) | ツーバイフォー工法(枠組壁工法) |
|---|---|---|
| 構造の基本 | 柱・梁で荷重を受ける「軸構造」。筋交いや耐力壁で水平力に抵抗。 | 2×材フレーム+合板で「面構造」を形成。六面体で荷重・水平力を分散。 |
| 部材の製作・加工 | 現場調整が多い(近年はプレカットで精度・効率化)。 | 規格化された2×材・構造用合板を用い、パネル化しやすい。 |
| 施工の流れ | 建て方→梁桁組→耐力壁・金物→造作。工程が多く天候影響を受けやすい。 | 壁・床パネルを連結して箱を組む。組立中心で工程が簡素。 |
| 設計自由度 | 高い。開口計画や増改築の裁量が大きい。 | 規格前提で相対的に低め。大開口・間取り変更に制約が出やすい。 |
| 工期 | やや長め。現場加工・調整の度合いに左右。 | 短め。パネル化で上棟〜外皮閉鎖が早い。 |
| 品質のばらつき | 職人技能・現場条件の影響を受けやすい。 | 規格材・工場加工により均質化しやすい。 |
| 耐震・耐火・気密 | 設計・金物・耐力壁採用で高性能化可能(差が出やすい)。 | 面構造で一体性が高く、耐震・耐火・気密を確保しやすい。 |
| リフォーム適性 | 良好。構造と間仕切りを分けやすく改修しやすい。 | 構造壁が多く、間取り変更は制限されがち。 |
| 木材・地域材の活用 | 地域材(スギ・ヒノキ等)や意匠表現がしやすい。 | 2×材規格が中心。地域材活用は限定的。 |
| コスト感 | オーダー性が高く振れ幅あり(仕様・手間に依存)。 | 標準化・量産でコスト最適化しやすい。 |
| 適するニーズ | 自由設計・将来改修・地域材活用・意匠重視。 | 短工期・一定品質・性能安定・標準仕様重視。 |
※どちらが優れているかは一概に決められず、自由度・工期・コスト・性能・将来の改修計画などの優先順位で選択が異なります。
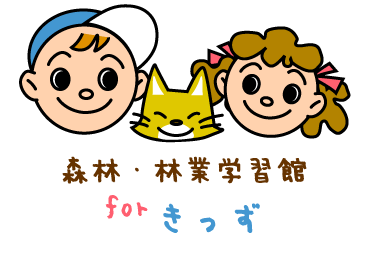
🏠 にほんの おうちは
どうやって たてるの?
〜 在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう)って
なに? 〜
みんなが すんでいる おうちは、どうやって できているか しってる?
にほんでは、むかしから「木(き)」を つかって おうちを たててきたんだよ。その中でも とくに たくさん つかわれているのが、
在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう) っていう つくりかた!
🌳 木を くみあわせて つくる おうち
この工法では、「柱(はしら)」や「梁(はり)」という 木の棒を たてたり よこに わたしたりして、
おうちの「ほねぐみ」を つくるよ。これが しっかりしているから、
おおきな かべが なくても じょうぶな おうちが できるんだ!
🧱 いろんな ちいきで ちがうつくり?
在来軸組工法は、ちいきによって すこし ちがったつくりを していることもあるんだよ。
たとえば…
・ゆきが たくさん ふる ところでは、ゆきの おもさに たえるように 屋根(やね)を きつくしたり
・じしんが よく おこる ところでは、ゆれに たえられるように すじかい という ぶざいを 入れたり
じつは、その まちに あった つくりかたを 工夫しているんだね!
🌲 つかわれる木にも ちがいがある!
おうちを つくる木も、いろいろ あるよ!
・にほんでは、スギ や ヒノキ が よく つかわれているよ。
・木の においや 手ざわりを たいせつにする おうちも あるんだって🌿
・地元の「地域材(ちいきざい)」を つかうことで、その土地の森を いかすこともできるよ!
💪 じしんにも つよい!
むかしの工法(こうほう)だけど、いまのぎじゅつと くみあわせると、じしんにも とっても つよいおうちが つくれるよ。
たとえば、
・金物(かなもの)という しっかりした つなぎパーツを つかったり、
・工場で 木を あらかじめ けずっておく「プレカット」で、ピッタリ くみあわせられるんだ!
🏡 まとめ
在来軸組工法(ざいらいじくぐみこうほう)は、にほんで むかしから つかわれている、木のほねぐみで おうちをつくる方法です。地域にあわせた くふうや、自然の木を いかした すてきな おうちが たてられるよ!

